「新婚生活で新しく家電を購入するけど、家電って高いよなぁ…」
「家電を新調するのに安く買う方法はないかしら」
新婚生活で家電を新調する際に、何も考えずに購入すると300,000円をムダに払ってしまう可能性があります。
ドラム式洗濯乾燥機と冷蔵庫を購入する際に、何も考えずに新型を購入した場合と、少し工夫して購入する場合を比較してみると、約300,000円も違いがあります。
つまり、家電購入する際の工夫の仕方を学ぶだけで、約300,000円もお得にすることが可能なのです。
300,000円って新婚生活では何かとご入用ですよね。新婚旅行で30万円も多く払えれば、ヨーロッパ諸国にクルーズ旅行なんかに行けたり、結婚式の会場をグレードアップしたり、子供の学費として補填することも可能でしょう。
また、1年前の型落ち家電で比較した場合でも同モデルのものを合計で86,000円程度お得に購入できました。
新婚生活をこれから始める人は家電の購入方法を知っておくのは重要ですね。
今回は、新婚生者向けに、家電の安い購入方法について解説します。
この記事で学べることは?
- 新婚生活で家電をケチっては行けない理由が学べる
- 新型家電と型落ち家電を購入した際の金額の比較が学べる
- 家電を賢く購入する方法について学べる
新婚生活は家電を買い直す時期!ここでケチったら大喧嘩になる
当然ですが、新婚生活では新しい生活が始まるため、家電を買い直す時期でしょう。
共働きの夫婦の場合は、家電で時短するか否かが、夫婦仲の良さを決定してしまいます。
極力最新型の家電を揃えておいた方が良いでしょう。
新婚生活の場合、家電選びで夫婦仲に亀裂が入ってしまう可能性もあります。
なぜなら、家電選びには最低でも下記3つの基準が存在するからです。
- 値段を求めるのか
- 機能を求めるのか
- 部屋にマッチしているか
部屋にマッチしているかは各人のセンスになるので、どうすることもできません。
しかし、値段と機能は両方とも成立させることは可能なのです。
新婚生活で家電を普通に購入した場合と安く購入した場合の比較
大きめの家電を購入する時に、最新の家電を普通に購入するか、それとも安く購入するかによって、支出額が10万円近く変わって来ます。
冷蔵庫とドラム式の洗濯乾燥機を買う際をケース分けして比べてみると、最大で30万円ほど違うことが明らかになりました。
新婚生活で最新の家電を購入した場合
新婚生活で何も考えずに家電量販店に行き買い物をした場合を考えてみましょう。
下記は2019年発売モデルの中で、一番オススメされている物を比較してみました。
- 冷蔵庫(容量455リットル・2019年6月発売):232,686円
- 洗濯乾燥機(容量11kg・乾燥6kg・2019年8月発売):296,870円
合計すると529,556円になります。最新型の家具を揃えるのは高く付くという訳ですね。
当然、他にも高いものはありますが、参考値としては良いかなと思います。
新婚生活で普通に家電を購入したケース
最新のは良いから少し型落ちの物を選んだ場合はどうなるでしょうか?
1年前の2018年発売モデルで比較してみると、約20万円も違うことがわかりました。
- 冷蔵庫(容量475リットル・2018年08月):平均139,200円
- 洗濯乾燥機(容量12kg・乾燥6kg・2018年09月発売):平均183,000円
合計金額は322,200円となります。
1年の型落ち品を選ぶだけでも、20万円程度の節約になります。意外に大きいですよね。
新婚生活で家電を安く購入したケース(私が購入した実際のケース)
型落ち品を購入してかつ、工夫して安く購入した場合はどの様になるのでしょうか?
上記と同じ家電を、私が実際に購入した金額は下記のとおりです。
- 冷蔵庫(容量475リットル・2018年08月):実質96,000円
- 洗濯乾燥機(容量12kg・乾燥6kg・2018年09月発売):実質143,513円
安く購入した場合、合計すると、239,000円になります。
さらにクレジットカードのポイント還元が1.25%あったので、約3000円程度お得になり、236,000円程度の出費に収まったのです。
型落ち家電を安く購入するようにしたら下記のとおりお得になりました。
- 新型の家電を購入していた場合と比較:約300,000円程度お得
- 型落ち家電を工夫せずに購入した場合と比較:約86,000円程度お得
新婚生活で家電を安く購入する方法
私は新型家電と比較すると約30万円ほどお得に購入することができましたし、1年の型落ち家電でも約8.6万円も安く購入することができました。
新婚生活で家電を安く購入する方法をご紹介します。
1年年前の型落ち家電を購入する=約半額になるものもあり
機能面でこだわりたいから最新の家電を購入したいという気持ちもわかります。
しかし、結論から言えば1年違うだけでは大した新機能がないのが実情です。
お得に購入したい場合は、本当に欲しい機能がある場合以外は、1年前の家電を積極的に購入するようにしましょう。
最新の家電と1年前の家電を比べると、だいたい半額程度の差が生まれています。なぜなら、家電は毎年新しいモデルが発売されるからです。
例えば、冷蔵庫や洗濯乾燥機であれば8月〜9月にかけて製品の入れ替えが起こります。そのため、8月〜9月ごろになれば、1年前の製品がかなり安値で購入することができるのです。
大型家電の場合は8月〜9月にかけて製品が入れ替わる可能性が高くなります。そのため、この時期には1年前の家電購入を狙いましょう。
常に最安値をチェックしよう
家電購入を検討したときは、だいたい1ヶ月くらい前から最安値をチェックすると良いでしょう。
私が使用したのは王道サイトである価格ドットコムです。気になった家電の価格推移グラフを見て、どの程度の値段になるのかを常に確認していました。
あるドラム式洗濯乾燥機の推移ですが、下記のように価格が推移していることがわかります。
このグラフの推移から、いくらぐらいで購入できれば得なのかを考えて、戦略を練っていきます。
買いに行ける場合:家電量販店めぐりをして値下げする
家電量販店まで買いに行ける場合は、家電量販店がたくさんある地域に行き、家電量販店めぐりをして値下げ交渉を行いましょう。
家電量販店が密集している東京都内の地域といえば、池袋、渋谷、新宿などがあります。これらの地域には家電量販店がたくさんあるので、店員さんを見つけて声をかけてみましょう。
声をかける際には「価格コムで○○円って見たんですけど、安くなりませんか?」という風に値段を伝えてみると良さそうです。
一旦退散するときは「他店を見てきます」というのではなく、「高額な買い物なので検討させてください」などと言って退散すると良いでしょう。
1つのお店で大体の金額が聞ければ、今度は2つ目のお店や3つ目などをめぐり、最安値で売ってくれそうなところを探してみると良いでしょう。
買いに行けない場合:ネット通販を上手に活用する(私のケース)
買いに行けない場合はネット通販をうまく活用するしかありません。
しかし、個人的な感想としては、ネットでの通販でも、ショップ巡り以上の値下げが期待できるかなと思います。
下記は、私が行ったネット通販を上手く活用してお得に家電を購入した方法を解説します。
まずはセール情報を検索します。
特にセールを気にするのは、
- 家電量販店のセール情報(ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダ電機など)
- Amazon関連のセール情報
- 楽天のセール情報
価格コムで分析してみると、上記のセールの時に購入したほうが、ポイント還元も含めると安いケースがあります。
また、価格コムの最安値のお店は知名度もそこまで高くないお店もあります。
昔、価格コムで見つけた最安値の中古パソコンを購入したら1ヶ月で故障してしまい、お店側からの返信もなかったこともありました…。
家電は比較的長い期間付き合うものであり、家電量販店や大手の通販サイトの方が保証がしっかりあります。
そのため、やすさも大切ですが信頼性で選んでいるのです。
今回の家電購入の場合は、丁度ビックカメラで決算セール中だったので、ビックカメラで購入しました。
もちろん、楽天・Amazon・ビックカメラのポイント還元から実質的な値段を計算して購入を決めたわけです。
そして、クレジットカードはジャックスのREXカードを使用して、クレジットカード自体のポイント還元率も1.25%にしました。
高還元率で、年会費もないため、REXカードは非常に使いやすいオススメのカードです。

新婚生活では家電を安く購入しよう
新婚生活は、家電を買い換える時期です。
しかし普通に家電を購入する場合、工夫して家電を購入するよりも、300,000円も余分にお金を支払う可能性もあるのです。
工夫して家電を購入する方法とは下記のとおりです。
- 1年前の型落ち家電を選ぶ
- 価格コムで家電金額の推移をチェックする
- 家電量販店に行けるなら家電量販店めぐりをする
- 家電量販店に行けないならセール情報をチェックし、実質ポイント還元も含めて比較する
家電を購入する際に、少し工夫をすれば、非常にお得に購入することも可能です。
新婚生活で家電を安く購入しようと考えている人の参考になれば幸いです。
以上、新婚生活で家電を安く買う?損を防ぐ賢い買い方【30万円の節約】を解説しました
最後まで読んでいただきありがとうございました。
>>【節約しないと大損してるよ?】
ちょっと節約の知識を知るだけで、毎月の生活を最低でも1万円以上節約が可能?
1年で12万円。10年で120万円になる節約の知識を解説中!
20代から知っておきたい節約術の記事一覧は下記になります!




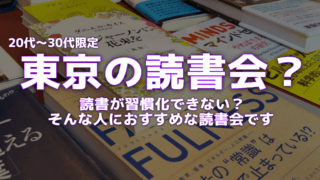
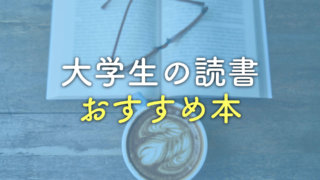
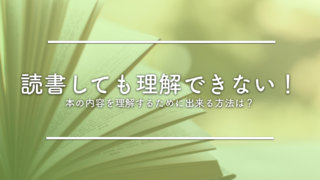




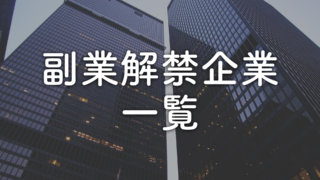


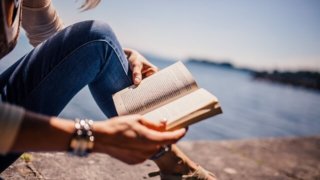
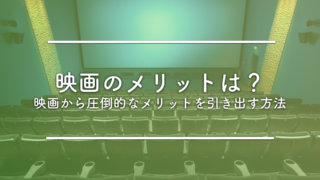




コメント